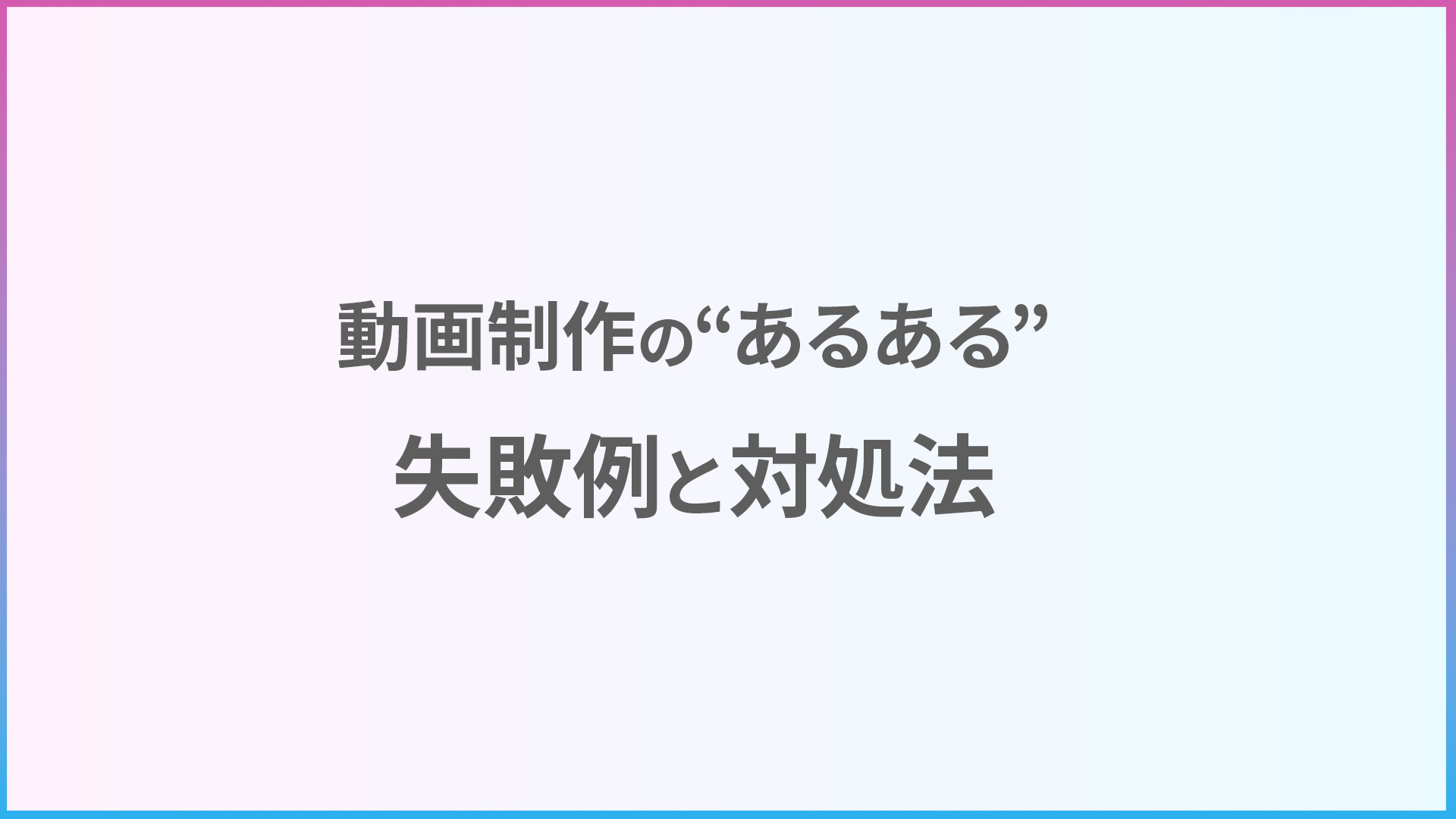企業がプロモーションや採用活動、社内向け研修などで動画を活用するケースが増えています。しかし、「動画」を初めて制作する際や、慣れないまま取り組んでいると、様々な“あるある”な失敗例に陥りがちです。そこで今回は、動画 失敗例として代表的なパターンを挙げ、それぞれの対処法を具体的に紹介します。
1. 目的が曖昧なまま進める
失敗例
- 「何となく動画を作ってみよう」という感覚でスタートしてしまい、具体的な目的が定まっていない。
- 結果として「企業イメージ向上」「採用強化」などの大きなくくりだけが先行し、ゴールを測定する指標(KPI)が不明瞭。
対処法
- 狙いを明確化:たとえば「新製品の認知度を1か月で○%向上させる」「採用サイトへの流入数を○%増やす」といった、達成したい具体的な目標を設定する。
- KPIの設定:再生回数、クリック率、問い合わせ件数など、数値化できる目標を設定してモチベーションや方向性を維持。
2. ターゲットを誤って設定する
失敗例
- 想定する視聴者の年齢層・ニーズを考慮せず、「とにかく社内の偉い人や関係者の要望を盛り込みすぎてしまう」。
- 結果として、メッセージ性が弱く視聴者に刺さらない映像になり、再生回数やエンゲージメントが伸び悩む。
対処法
- ペルソナ設計:視聴者を具体的にイメージする。年齢、職業、興味関心、ライフスタイルなどを細かく設定して、必要な情報・演出を絞り込む。
- 市場調査&ユーザーインタビュー:実際の顧客や見込み客から声を集めることで、よりリアルな視聴者ニーズを掴む。
3. ストーリーや構成に一貫性がない
失敗例
- 企画段階でストーリー構成を固めずに撮影や編集を始めるため、「何を伝えたい動画なのか」分かりづらい状態に。
- シーンがとびとびで繋がりが弱く、視聴者の理解が深まらない。
対処法
- 台本・シナリオの作成:動画全体の起承転結や、登場人物の役割、演出のタイミングなどを事前に設計する。
- ストーリーボードの活用:絵コンテを用いて動画の流れをビジュアル化。関係者全員でイメージを共有し、撮影時や編集時の手戻りを防ぐ。
4. 社内調整に時間をかけすぎて製作が遅延する
失敗例
- 動画の企画・編集段階で、部門ごとに別々の要望が提出され、意見が収束しない。
- 「意思決定者が多すぎる」「合議に時間がかかりすぎる」ことで、完成が大幅に遅れる。
対処法
- 担当窓口を一本化:企画と連携をとる責任者やチームリーダーを明確にして、決裁ルートを短縮する。
- スケジュールの明確化:修正回数や確認プロセスの締め切りを決め、プロジェクト管理ツールなどを活用して進行状況を可視化する。
5. クオリティを追求しすぎて予算オーバー
失敗例
- 企業イメージを高めようと、撮影機材・スタジオ・制作スタッフに過剰投資。
- 後から見積もり額に大幅な差異が発覚し、社内でトラブルに発展するケースも。
対処法
- 適正な目標設定:動画の使用目的や媒体(SNSなのか、展示会なのか)によって必要なクオリティは異なる。目的に見合った範囲で機材やスタッフを手配する。
- 見積もりの複数比較:外注を検討する場合は、最低でも2~3社から見積もりを取り、コストとスキルのバランスを比較検討する。
6. 動画公開後の活用策が不十分
失敗例
- 制作した動画を自社サイトやYouTubeにアップするだけで、効果測定やプロモーションを実施しない。
- 公開して満足してしまい、SNS拡散や広告運用などの露出施策がおろそかになる。
対処法
- マーケティング施策との連携:SNS広告、メールマーケティング、ランディングページの最適化など、動画を効果的に拡散・活用するための施策を事前に考える。
- 効果測定と分析:再生回数、視聴維持率、コンバージョン率などの指標を追いかけ、定期的に改善策を打つ。
まとめ
企業動画の制作には多くのプロセスが関わるため、失敗例は決して珍しいものではありません。目的やターゲットの明確化、ストーリー構成の統一感、社内調整のスムーズさ、そして予算管理と公開後の活用まで、一つひとつのステップをしっかりと押さえることが大切です。今回紹介した“あるある”な失敗例と対処法を参考に、ぜひ次回の企業動画